有川浩の「キケン」という小説の文庫版が書店に並んでいたので、有川浩を作者買いする私は迷わず手に取った。
「塩の街」の初版が書店の棚に並んでいた時から知っている作家で、私の人生の多分10%くらいは彼女の小説に影響されているかもしれない。
「さあ、今回はどんなラブストーリーが待っているのだろうか? 理系技術モノっぽいし、どんな技術が登場するのか楽しみだ」
……そんな私の勝手な予測は、良い意味でがっつりと裏切られることになった。そうか、有川浩ってこんな作品も書けたんだ。

「キケン」のあらすじ
「キケン」とは、危険のことではなく(ある意味そうなのだが)、物語の舞台となる「成南電気工科大学」にある研究部(サークル)である、「機械制御研究部」の略称のことである。
物語はキケンにおけるアクの強い登場人物たちによりどんどん突き進み、各章で綴られる青春エピソードが読者に一種の活力を与えてくれる。
そして最終章では、ちょっとした仕掛けにより思わず涙腺が緩む展開もある……エンタメ小説としての一つの完成形が、この一冊の本に詰まっているといってもいいだろう。
ネタバレを少し含む感想を書いていく
「青春」とは何だろうか?
この本を読むと、間違いなくその感想が沸いてくるに違いない。
作中に登場する人物たちは、皆紛れもなく、その辺にいる冴えない男子大学生たちだ。
逆ナンされて付き合った彼女と2ヶ月で別れる大神然り。女子大の学園祭のヘルプに呼ばれたのに、チャンスをモノにできなかった後輩しかり。
ごく普通の大学生たちが当たり前に恋愛する中、この作品の大学生たちは、恋愛に関してはとにかく不器用だ。
……でも、彼らは間違いなく「青春」しているのである。この作品を一言でまとめ上げるならば、間違いなく「青春」という単語を使いたくなるぐらいに。
何がそんなに青春に感じるのだろうか?
ああ、青春ってこういうことをいうのか。
この本に登場する人物である「お店の子」元山も、同期の池谷も、そして先輩の上野も大神も、みんなそれぞれの目線で「青春」している。
物語でひときわ輝いて見えるのは、なんといっても元山だろう。学園祭の模擬店であるラーメン店で、「奇跡の味」を「奇跡」から「当たり前」に変えた男だ。彼も最初のうちは、上野と大神の態度に戦々恐々としながらも、徐々に自分の立ち位置を確保していった人間である。
模擬店の店長に任命された元山の輝きっぷりはハンパじゃなかった。
この作品で私が一番好きなシーンは、元山がスープの味を一人で研究しつくし、それを「キケン」メンバーに展開する場面までの一連の流れだ。
元山が作ったスープを、先輩の上野が試食する。
「このスープはコンスタントに作れんのか?」
「あ、はい」(中略)「でもちょっと問題があって……」
「それは後で聞く、作れるんだな?」
「はい」
そこからが上野らしい。
「今から突貫で立て看作れ。煽り文句言うぞ、控えろ。――看板に偽りなし!『奇跡の味』、今年は初日から最終日まで! 以上な」
もうこのシーンだけで、ラーメンを食わずとも腹が膨れるというものであろう。実に有川らしい、絶妙な人物描写ではないか。そして、そんなふうにハッパをかけられた元山は、
「うるせえ! お前らを湯に浸けたって垢しか出てこないのに鶏ガラはスープの要になるダシを出してくれるんだぞ、どっちが偉いと思ってるんだ!」
「お店の子」のプライドにかけて、模擬店のラーメンに全身全霊を注ぎ、同期たちにラーメンの量産方法を指南する。この場面だけを切り取ってみれば、元山の貫禄は上級生の上野らを超えていたとさえ思える。それが同期たちに伝播し、結果として「キケン」の模擬店は過去最高の売上を樹立した。
樹立した後はもちろん万札で酒を買ってきて、前後不覚になるぐらい打ち上げ。
こんなふうに、どんなことにも「ガチ」になって、汗臭い感じが漂いながらも、全力で「今」を楽しんでいるキャラたちを眺めるのは最高の快感だった。
「キケン」に見る、有川浩らしいところ・そうでないところ
正直に告白すると、私は先日、久々に有川浩作品の「フリーター、家を買う。」を読んだ。その時に思ったのは、「あぁ……最近は悪い意味でエンタメ小説に落ちてしまったか……」という悲しい感想だった。
自衛隊三部作のときも、図書館戦争のときも、阪急電車のときも、有川作品のキャラはカッコ良かった。アクが強かった。
そのアクが、「三匹のおっさん」「県庁おもてなし課」ぐらいから、微妙に劣化しているように感じつつあった。年にするとちょうど2009年ぐらい。プロの作家といえど、ある時期を境に作品の方向性が変わってしまうということはよくある。有川浩もご多分に漏れずそうなったのかなぁ、めちゃくちゃ売れたしエンタメ路線でやっていくのかな、とも感じた。
それがどうだろう。2011年作の「キケン」には、そのアクが復活している。
なにより、名物である超暴走役とブレーキ役の構図が再び出来上がっていることに、私は軽く感動を覚えたのである。こんな作品を読み漏らしていたとは……。
暴走役は、とにかく全力で物語のアクセルを踏み込み、ガンガン読者を魅了する。しかし暴走役は無敵ではなく、どこかで弱みも持っているし、不器用な部分だってある。そんな時にフォローするブレーキ役がいる。
自衛隊三部作、特に「海の底」ほど明確に立場が分かれているわけではないし、時々ミックスしているものの、この作品における大神と上野の関係は、それを軽く彷彿させるものがあったように感じる。
有川作品はとにかく、このアクセルとブレーキの使い分けが上手いのだ。
一方で、やはり少し「珍しいな」と感じるのは、登場人物の心理描写だ。
この作品は元山が書いたという体で描かれているから仕方ないが、有川作品特有の「透明なカメラ」描写は少ない。「透明なカメラ」とは、「図書館戦争」シリーズ外伝「図書館内乱」のあとがきで有川自身が使っている単語で、「作品世界を撮影している」という意味だ。作者は透明なカメラなので、いつでもどんなときでも登場人物の外観、内面に踏み込めるということだと思う。
より具体的にいうと、残酷なまでの心の声の活字化である。
「フリーター、家を買う。」では健在だし、それ以外の作品でも「心の声」は健在だ。だが、「キケン」には少ない。でも多分それはこの作品については正しい。なぜなら、キャラクター同士の衝突というものがこの作品にはほとんど無いからだ。
この作品では、それぞれのキャラクターたちが共通して(時には理不尽な)目標に立ち向かっていくものの、それはいわゆる勧善懲悪的な構図ではなく、あくまで青春の一コマとしてコミカルに描かれている。だから、ココロとココロの衝突は不要なのだ。
そして、ココロとココロの衝突なくしても、この作品は面白い。
なぜなら、それは「青春」を真正面から描ききれているからだと思う。
青春とは、
恐らくそれは、「向こうを見ずに目の前のことに全力を集中させて取り組む」姿勢だ。
個人にとって青春だと思える時期はそれぞれ違う。中学生かもしれないし、高校生かもしれないし、大学生かもしれない。だが恐らく共通して言えるのは、「その時は、そのことしか考えていなかった」ということだ。
- 高校や大学時代の恋愛で、相手の将来の社会的地位や結婚後の子育て、老後の資金まで考えて付き合ったことがあっただろうか?
- どこかに出かけるにしても、あれやこれやと準備し、旅行代理店ばりの綿密なプランを立てて常に周りに気を使い続けることをしただろうか?
- 酒を飲むときに、翌日のことを考えて飲む量を加減しただろうか?
上記の問いに全て「はい」と答えられる人は、おそらくそうはいないと思う。
多くの人は、向こう見ずに告白し、大抵は玉砕し、よしんばOKを貰えたとしても刹那的だが濃厚な時間を過ごしてご破斬となるなり、突発的に出かけて何かの予定をすっぽかしたり、自分の予測の甘さに愕然としてみたり、飲み会の後で超絶他人に迷惑をかけたり、そんな時代を送ってきたのではないかと。
もちろん、青春していた頃の自分は、青春なりにいろいろと考えて生きていたはずだ。しかし、それでもやっぱり、後から振り返ってみると、それは「青春」なのだ。色々と足りていないものである。
今になってみて思うのである。「どうしてあの頃はあんな馬鹿げたことに一生懸命だったのだろう?」と。
そして、同時にこうも思うのである。「また、あの頃みたいに一生懸命になれたらいいのになぁ」と。
そんな、ふとした瞬間に頭をもたげる感情を静かに盛り上げてくれるのが、私にとっては本作品「キケン」だった。
本作品は、有川作品にしては珍しく恋愛要素がほぼ描かれていない。リアルだ。私のような人間だからこそ、「リアル」に感じてしまうのかもしれないが。
もう一度青春はできなくとも、青春を追体験することはできる。そんなことを感じた一冊だった。
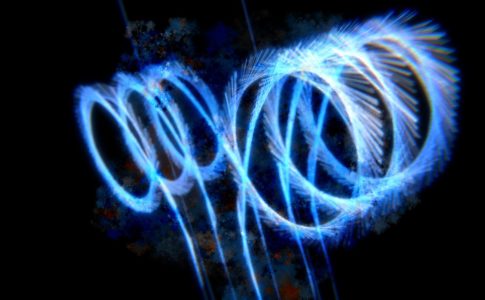

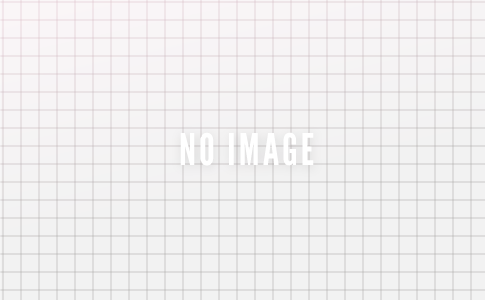
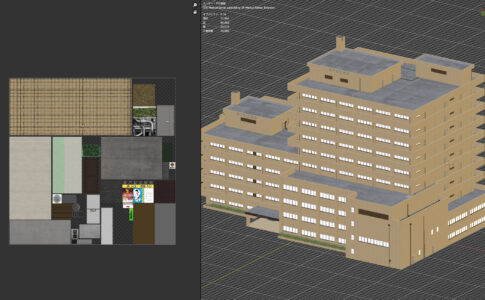



 神乃木リュウイチといいます。
神乃木リュウイチといいます。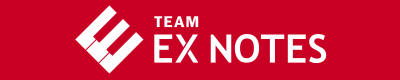
コメントを残す